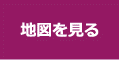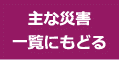御嶽火山1979年噴火
御嶽火山は約2万年前以降、活動のほとんどない比較的静穏な時期を続けていたため、当時は“死火山”扱いされていたが、1979年に突然の水蒸気爆発が起き、活火山の定義に見直しがなされるきっかけとなった。この活動は午前5時頃の水蒸気爆発に始まり、14時頃に最大となりその後衰退し、噴出物の総量は約20数万トンと推定されている。約1,000mの高さまで噴き上げられた噴煙は北東へ向かって流れ、軽井沢や前橋市まで降灰した。この噴火で直接的に受けた大きな被害はなかった。なお、これと同じ噴火口から1991(平3)年と2007(平19)年にごく小規模な水蒸気噴火があったようで、火口周辺のみ降灰した。
火砕流
火山噴火において噴煙と同じものが溶岩のように地面に沿って流れる現象である。噴煙の中には火山灰(ガラス片)のほかにマグマのかけらに相当する軽石や噴火の際に取り込まれる既存の岩石などが入っており、それらの固体をまとめて火山砕屑物といい、それらが火山ガス(ほとんど水蒸気)と混ざった状態で地表面に沿って流れる現象である。これによってもたらされた堆積物を火砕流堆積物という。火砕流はきわめて流動性に富む状態で運ばれるために、高温状態のまま高速で運ばれることになり、溶岩流などの噴火現象に比べるとはるかに危険な現象と理解しておかなければならない。
地質年代