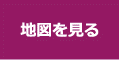火砕流
火山噴火において噴煙と同じものが溶岩のように地面に沿って流れる現象である。噴煙の中には火山灰(ガラス片)のほかにマグマのかけらに相当する軽石や噴火の際に取り込まれる既存の岩石などが入っており、それらの固体をまとめて火山砕屑物といい、それらが火山ガス(ほとんど水蒸気)と混ざった状態で地表面に沿って流れる現象である。これによってもたらされた堆積物を火砕流堆積物という。火砕流はきわめて流動性に富む状態で運ばれるために、高温状態のまま高速で運ばれることになり、溶岩流などの噴火現象に比べるとはるかに危険な現象と理解しておかなければならない。
溶結凝灰岩
火砕流によりもたらされた堆積物が溶結作用を受けると、その程度により強溶結、弱溶結、非溶結凝灰岩となり、一般には強溶結凝灰岩をさしていう。おもに火山灰が集まって形成された岩石ではあるが、強く圧密化した岩石となり、きわめて堅硬な岩石となる。
火山灰流シート
構成する固体物質のうち50%以上が火山灰(径2mm以下の火山砕屑物)からなる火砕流を火山灰流(ash flow)といい、それによる堆積物が一定の厚さで連続した単位として「層」をなしたものを火山灰流シート(ash flow sheet)と呼ぶ。この「層」には鉱物組成あるいは化学組成において連続的な変化をともなうもの、ほぼ均質なもの、岩相上の差異をともなうものなどがあるが、1つの火山層序ユニットを構成している。
地質年代