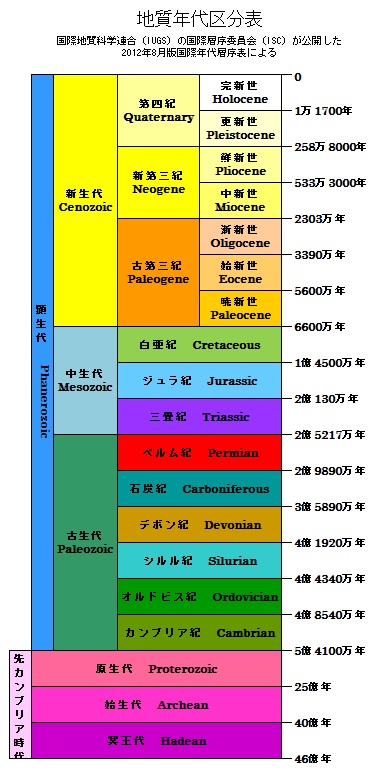| 施設名 | 金生山化石館 | きんしょうざんかせきかん |
| 地図 | 地図を見る | |
| 場所 | 大垣市 | |
| 電話 | 0584-71-0950 | |
| HP | https://www.city.ogaki.lg.jp/0000000664.html | |
| 管理者 | 大垣市(指定管理施設) | |
| 開館年月 | 1985(昭60)年 | |
| 施設概要 | 赤坂尋常小学校校長、戦後旧赤坂町の初代公選町長を努めた故熊野敏夫氏が長年にわたり収集した膨大な金生山の化石標本の収蔵と展示を目的に設立された施設である。1964(昭39)年3月に開館された後に1976(昭51)年に旧赤坂商工会議所に移転し、1985(昭60)年に大垣市からの資金援助を受けて赤坂商工会が現在の建物を建設した。1996(平8)年に市に寄贈・移管されて指定管理者のもとで管理運営されていたが、2019(平31)年4月から市直営の施設として運営されている。大型二枚貝化石シカマイアをはじめとして金生山から産する約700点の化石(鉱物も含む)が展示されており、体験活動や講座なども実施しながら、金生山の自然と文化にかかわる資料の収集・整理・保存が進められている。 | |
| ジオ点描 | ドイツの学会誌に日本産の化石が最初に学術論文として記載されたのが金生山産のフズリナの新種であったことから、金生山は「日本の古生物学発祥の地」と呼ばれ、化石愛好家にとっては憧れともいわれる場所である。そうした背景のなかでここから産する化石に特化して展示・保管がなされた施設であり、学術的にも歴史的にも貴重で、保存の良い多種多様な化石を見ることができる。 | |
| 出版物 |
|
|
| 写真 |  |
金生山化石館の入口 (撮影:小井土由光) |
| 写真 |  |
金生山化石館の外観 (撮影:小井土由光) |