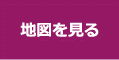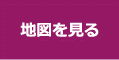飛騨帯構成岩類
飛騨帯は、岐阜県の北部から北陸地方へかけての地域に広がる変成岩類と花崗岩類からなる地質帯である。ただし、これらの構成岩類がこの地域のどこにでも分布しているわけではなく、それ以降に形成された岩石類に覆われたり貫かれているために、実際にはかなり限られた地域にだけ分布する。変成岩類は総称して「飛騨片麻岩類」と呼ばれ、それらを形成した広域変成作用の時期についてはいくつかの見解があるが、おおよそ3億年~4億5000万年前(古生代石炭紀・シルル紀・デボン紀)と2億4000万年前ごろの少なくとも2回にわたり重複した変成作用で形成されたとされている。花崗岩類はこれまで「船津花崗岩類」と呼ばれ、1億8000万年前(中生代ジュラ紀)に飛騨外縁帯構成岩類の分布域にまで及ぶ範囲に一斉に貫入したことで飛騨片麻岩類に熱変成作用をもたらしたと考えられてきた。しかし、それらの中には古い年代を示す岩体もあり、一律に扱うことができないことがわかってきたため、それらの形成時期を少なくとも2期に分けて区別するようになった。変成岩類も花崗岩類も複数回におよぶ複雑な過程を経て形成されているために、すべての飛騨帯構成岩類を全域にわたって一定の基準で表現することはかなりむずかしいことから、ここではそれらを「飛騨変成岩類」、「飛騨花崗岩類」と呼び、それぞれを6種類と10種類の岩相に区分することで表現する。そのため1つの岩相で示される岩石の中にも別の変成・深成作用で形成された岩石が含まれている場合もある。
三田洞神仏温泉(長良川温泉)
1959(昭34)年に岐阜市三田洞において簡易水道工事のボーリング掘削中に湧出し、岐阜市がこれを活用して保養施設として建設したもので、現在は指定管理者により運用されている。“神仏温泉”は近隣にある三田洞弘法 (法華寺)と白山神社に因んだ名称であり、美濃帯堆積岩類中に湧出する含鉄泉である。もともとは無色透明の冷水であるが、空気に触れると赤褐色に変化するため含鉄泉独特の濁り湯となる。これと同じ含鉄泉は飛騨古川の市街地中心部にある古川温泉においても湧出しているが、いずれにおいても含鉄泉が湧出する理由は正確にはわかっていない。なお、長良川鵜飼を中心とする観光地となっている長良川河畔にあるホテル・旅館は「長良川温泉」として知られるが、温泉が河畔に湧出しているわけではなく、1968(昭43)年に三田洞神仏温泉を源泉として引湯されて利用されているものである。
地質年代