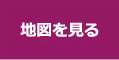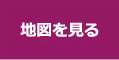飛騨帯構成岩類
飛騨帯は、岐阜県の北部から北陸地方へかけての地域に広がる変成岩類と花崗岩類からなる地質帯である。ただし、これらの構成岩類がこの地域のどこにでも分布しているわけではなく、それ以降に形成された岩石類に覆われたり貫かれているために、実際にはかなり限られた地域にだけ分布する。変成岩類は総称して「飛騨片麻岩類」と呼ばれ、それらを形成した広域変成作用の時期についてはいくつかの見解があるが、おおよそ3億年~4億5000万年前(古生代石炭紀・シルル紀・デボン紀)と2億4000万年前ごろの少なくとも2回にわたり重複した変成作用で形成されたとされている。花崗岩類はこれまで「船津花崗岩類」と呼ばれ、1億8000万年前(中生代ジュラ紀)に飛騨外縁帯構成岩類の分布域にまで及ぶ範囲に一斉に貫入したことで飛騨片麻岩類に熱変成作用をもたらしたと考えられてきた。しかし、それらの中には古い年代を示す岩体もあり、一律に扱うことができないことがわかってきたため、それらの形成時期を少なくとも2期に分けて区別するようになった。変成岩類も花崗岩類も複数回におよぶ複雑な過程を経て形成されているために、すべての飛騨帯構成岩類を全域にわたって一定の基準で表現することはかなりむずかしいことから、ここではそれらを「飛騨変成岩類」、「飛騨花崗岩類」と呼び、それぞれを6種類と10種類の岩相に区分することで表現する。そのため1つの岩相で示される岩石の中にも別の変成・深成作用で形成された岩石が含まれている場合もある。
八幡断層
上市の白鳥町付近から八幡町付近にかけての長良川は、大きな河川の上流部としては珍しく幅の広い谷底平野を形成している。長良川にダムが造られなかった理由の一つにこの広い谷底平野の存在がある。この谷底平野は、その西側をほぼ平行に北北西~南南東方向に延びる八幡断層の動きに関係して形成された。八幡断層の東側は数百m規模で相対的に沈降し、そこを長良川が流れるようになり、土砂が堆積して広い谷底平野になった。その反対に断層の西側は隆起し、浸食されて急峻な山地となっている。油坂(あぶらざか)峠道路をはじめとして八幡断層を横断して断層崖の急な斜面を横切る道路は数百mも登る峠道になっている。この断層は、長さや規模からして長良川上流地域において中心をなす活断層であり、2004(平16)年に政府の地震調査委員会は、この地域で地震が起こればマグニチュード7.3程度の規模になると報告したが、過去の活動を示す資料はほとんど得られていない。
地質年代