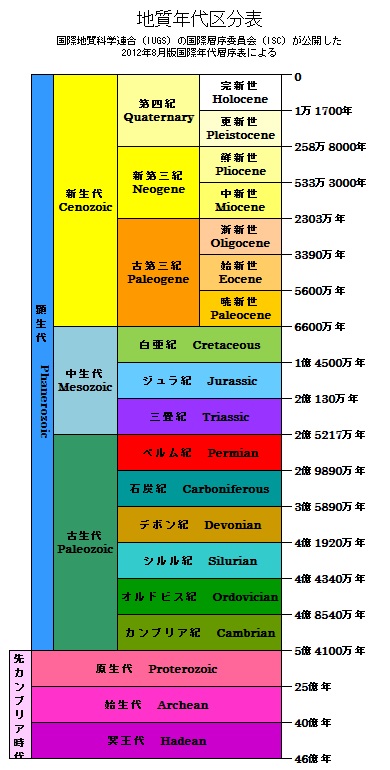| 項目 | 帰雲山大崩壊地 | かえりぐもやまだいほうかいち |
| 関連項目 | 事項解説>主な災害>土砂災害>帰雲山の大崩壊 | |
| 地点 | 大野郡白川村保木脇(ほきわき) | |
| 見学地点の位置・概要 | 富山方面へ向かう国道156号が白川村平瀬から鳩ヶ谷へ向かう途中の保木脇の集落を過ぎると、道路脇に「帰雲城埋没地」の大きな看板が立っている。そこを右手に入ると広場があり、そこに帰雲城跡を示す石碑がある。そこから対岸の山腹に大崩壊地が見え、それが帰雲山大崩壊地である。 | |
| 見学地点の解説 | ここは、1586(天正13)年の天正地震の震動によって崩壊したとされている帰雲山の大崩壊地からの崩壊物が山腹を流れ下った岩屑なだれによって、庄川沿いにあった帰雲城とその城下町を埋没させたとされている場所である。ただし、それらはいずれも確証のある話にはなっていないことに注意しておく必要がある。帰雲山周辺に分布する岩石は庄川火山-深成複合岩体の火山岩類で、おもに流紋岩質あるいは流紋デイサイト質の溶結凝灰岩からなり、それらが約5,400万年という形成年代値を示す白川花崗岩類(鳩ヶ谷岩体)によって貫かれて、強い熱変成作用を受けている。この花崗岩がこの場所に建てられている石碑として用いられている黒雲母花崗岩である。 | |
| ジオの視点 | 天正地震は中部地方のかなり広い範囲にわたって災害を起こしており、その震動をもたらした活断層の特定にいろいろな説が出されている。その一つに御母衣断層が動いて帰雲山の大崩壊と帰雲城の埋没伝説をもたらしたとする説が挙げられている。歴史時代の大地震であっても、日本でその原因となる活断層が正確に特定できるようになったのは明治時代以降になってからで、1891(明24)年の濃尾地震をもたらした根尾谷地震断層の活動が最初であり、江戸時代なるともはや怪しくなるのが実情である。 | |
| 写真 |  |
白川村平瀬にある道の駅「飛騨白山」からみた帰雲山大崩壊地 (撮影:小井土由光) |
| 写真 |  |
白川村保木脇の庄川河床付近に設置されている帰雲城址の石碑と帰雲山大崩壊地 (撮影:小井土由光) |