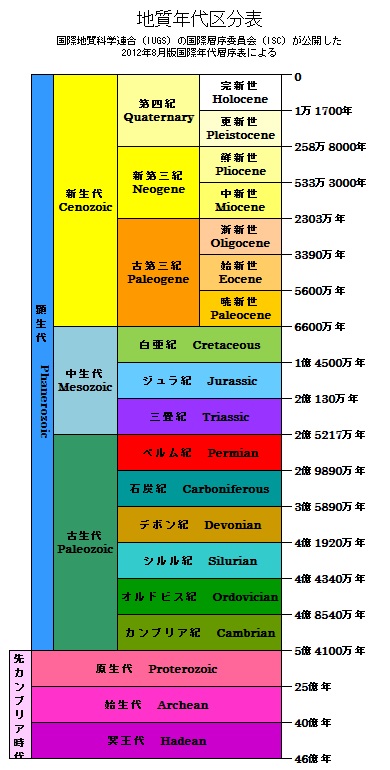| 項目 | 大滝鍾乳洞 | おおたきしょうにゅうどう |
| 関連項目 | 事項解説>地形・鍾乳洞>鍾乳洞>大滝鍾乳洞 | |
| 地点 | 郡上市八幡町安久田(あくた)2298 | |
| 見学地点の位置・概要 | 八幡町吉野において国道156号から千虎(ちとら)川沿いに県道328号安久田吉野線をたどるルートと、同じく八幡町穀見において国道156号から「公団幹線林道(旧名)八幡-下呂線」で安久田から縄文洞を経て入るルートがある。いずれのルートにも案内指示がある。 | |
| 見学地点の解説 | 郡上市八幡町から和良(わら)町にかけての地域には美濃帯堆積岩類の石灰岩が帯状に分布しており、地下には大小あわせて35洞にもなるとされる鍾乳洞が形成されている。大滝鍾乳洞はそれらの中の一つとして1969(昭44)年に発見され、東西方向に約270m,南北方向に約40m、高低差約100mの範囲に大きく4段にわたり広がっている鍾乳洞である。この鍾乳洞は断層に沿って水が集中して流れて大きな滝を地下に形成していることを特徴としており、なかでも最奥部の地下60mの位置にある“大滝”は約30mの落差をもち、豊富な水量を誇っており、観光洞としてのこの鍾乳洞のシンボルとなっている。全体に洞内を流れる水量が多く、泥が洗い流されて白色の透明度の高い鍾乳石類が多くみられる。 | |
| ジオの視点 | 県内に分布する鍾乳洞は、いずれも美濃帯堆積岩類を構成する石灰岩の岩体内に形成されている。しかし、石灰岩の分布域であればどこにでも鍾乳洞が形成されるわけではない。地下で石灰岩を溶かす地下水の水脈がなければ形成されない。すなわち石灰岩の中にそれなりの規模で割れ目系がなければならない。それに地下水の水位が絡んで何段にもわたる洞窟が形成されることになる。 | |
| 写真 |  |
大滝鍾乳洞の入口 (撮影:鹿野勘次) |