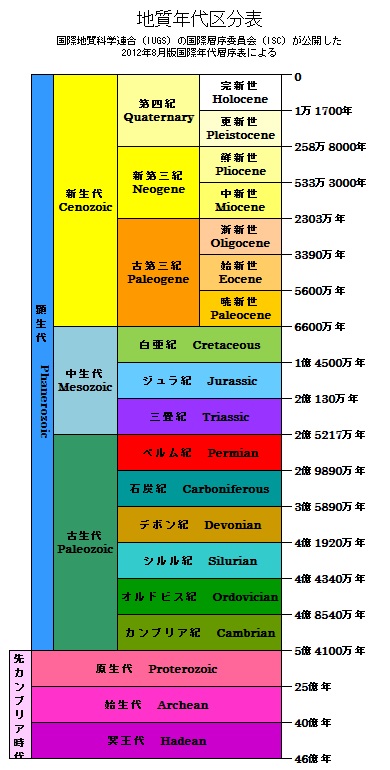| 項目 | 陶土鉱山 | とうどこうざん |
| 関連項目 | 事項解説>鉱山跡・資源>非金属資源>丸原鉱山 | |
| 地点 | 恵那市山岡町原 | |
| 見学地点の位置・概要 | 恵那市山岡町下手向(しもとうげ)から瑞浪市陶町(すえちょう)へ向かう県道405号下手向陶線の中ほどにあたる山岡町釡屋地区と原地区の間には、県道の南側(山側)にほぼ並走するように道路が延びており、その南側に沿って山地との間に陶土鉱山の採掘場あるいは採掘跡が広がっている。それらは道路面よりも深く掘り下げた凹地として荒涼とした景観を作っているが、鉱山敷地内とりわけ作業中の現場への立ち入りは、作業の妨げになったり危険防止もあり絶対に避けなければならず、許諾を得た上で可能な範囲からの遠望にとどめておく必要がある。 | |
| 見学地点の解説 | 鉱山の広がる低地には、地表に瀬戸層群の上部層である土岐砂礫層が、その下に下部層の土岐口陶土層がそれぞれ分布している。そのため鉱山は、土岐砂礫層を剥ぎとったうえで下位の土岐口陶土層を露天掘りしている。ただし、陶土層は限られた範囲にある堆積盆地内に分布しているため、そこを掘り尽くすと深い凹地となり、そこに水が溜まった池となっている。この採掘場の一番奥まった南端部では、破砕された白色の伊奈川花崗岩と黄褐色の土岐砂礫層が活断層の恵那山断層で接している。この断層は、南側の山塊が北側へせり上がるように上昇している逆断層で、その際に北側の土岐砂礫層は引きずられてめくれ上がるように急傾斜している。残念ながらその場所へは近づけないため、これらの状況は遠望せざるを得ない。 | |
| ジオの視点 | 陶土層は、周囲の花崗岩に含まれる長石類が風化して分解して粘土鉱物を生成し、それらが陥没盆地に流れ込んで堆積したものである。花崗岩には石英も多く含まれており、それらは風化されずに分解されないため、陶土層の中にそのまま含まれている。この石英粒が水に濡れると蛙の目のように見えることから、こうした陶土層は蛙目(がえろめ)粘土と呼ばれている。また、陶土層の中には、周囲に繁茂していた植物片がいっしょに流入して黒色の炭化木片として見られ、オオミツバマツやメタセコイアの大型の球顆も見られることがある。 | |
| 写真 |  |
山岡町原にある陶土鉱山 (撮影:小井土由光) |
| 写真 |  |
陶土鉱山敷地内に野積みされている陶土層の表面(石英粒と炭化木片が浮き出ている) (撮影:小井土由光) |