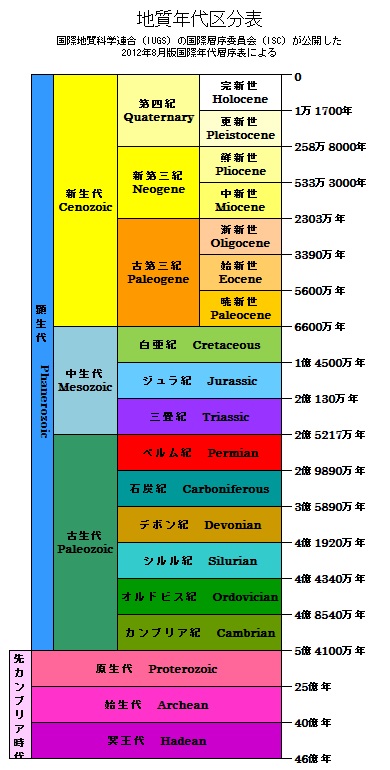| 項目 | 高木の立体交差 | たかぎのりったいこうさ |
| 関連項目 | 事項解説>活断層>岐阜・西濃地域>梅原地震断層(深瀬の湖) | |
| 地点 | 山県市高木 | |
| 見学地点の位置・概要 | 岐阜市街地から山県市方面へ向かう国道256号は、高富トンネルを抜けて山県市役所東交差点で県道79号関本巣線と交わる。そこを高富町市街地方面へ右折して300mほどで鳥羽川を渡る。その橋を扇橋といい、そこから下流300mほどに高木橋と呼ばれる小さな橋が架かっており、その右側(西側)に1mほどの段差で坂道が見える。その段差は川に直交する方向に通る梅原地震断層が動いたことでもたらされたものであり、それにより濃尾地震がもたらされたことに加えて、この付近一帯の生活環境に多大な影響がもたらされた。 | |
| 見学地点の解説 | 梅原断層は旧高富町の市街地北部を西北西~東南東方向に延びており、1891(明24)年に動いた際には、その南側にあたる地域を約1m上昇させる変位をもたらした。南流する鳥羽川は高木橋の位置で堰き止められた形となり、断層の北側一帯に「深瀬の湖」と呼ばれる湖を出現させた。湖は35日間も続き、その後も長く排水の悪い状態が続いたため、鳥羽川の東側に排水路(新川)を掘り、2kmほど下流で鳥羽川に合流させた。さらに1956(昭31)年には沈降した鳥羽川河床のかさ上げを行い、鳥羽川の西側地域の排水を目的として排水路を鳥羽川の下にくぐらせて立体交差(これを“伏越(ふせこし)”という)させて東側の新川に流すようにした。この立体交差は、断層運動により大地が大きく動いたことで水害がもたらされ、それへの対策として設けられた施設ということになる。ただし、現在さらに排水状況をよくするために改修工事がなされ、立体交差は取り除かれている。 | |
| ジオの視点 | 根尾谷断層系全体からみると、根尾谷地域の根尾谷断層は左横ずれ断層を主体としているのに対して、梅原断層は南側の隆起する縦ずれ断層を主体としている。トレンチ調査などにより明らかにされている活動周期も、前者が5,000年前後であるのに対して、後者はおおよそ倍にあたる10,000年前後と大きく異なる。濃尾地震を起こした断層運動はその周期の異なる断層が同時に動いたことで、きわめて大きな振動を長時間にわたって出し続けた結果ということになる。 | |
| 写真 |  |
山県市高木の高木橋における断層崖(軽自動車の位置に段差がある) (撮影:小井土由光) |
| 写真 |  |
大規模な改修工事前における鳥羽川の東側(新川側)からみた立体交差(鳥羽川堤防の奥に見える建物が山県市役所) (撮影:小井土由光) |