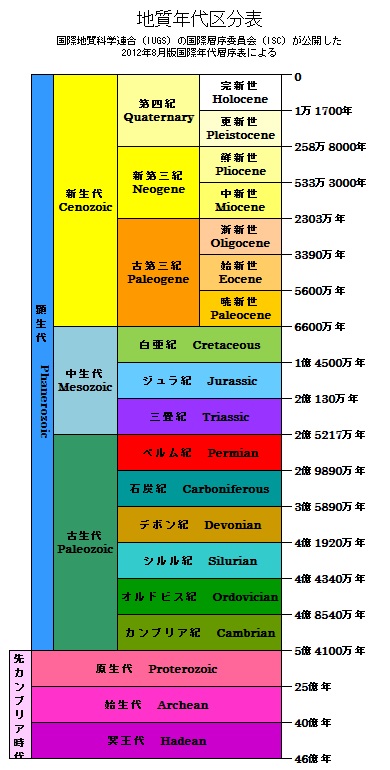| 項目 | 環流丘陵 | かんりゅうきゅうりょう |
| 関連項目 | 事項解説>地形・鍾乳洞>環流丘陵 | |
| 地点 | 美濃市立花(たちばな)/保木脇(ほきわき) | |
| 見学地点の位置・概要 | 長良川鉄道の湯の洞温泉口駅付近では、長良川対岸の立花海上(かいしょ)地区と駅南東側の東海北陸自動車道との間の保木脇地区にそれぞれ環流丘陵がみられる。前者は長良川に架かる立花橋から上流を望むと独立した小丘として確認できるが、後者は前者に比べて形態が明瞭ではなく、少し離れた長良川西岸から望むと確認しやすい。ここより上流の郡上八幡までの間には、美濃市上河和(かみこうわ)、郡上市美並町根村・大矢・苅安(かりやす)・赤池・深戸、郡上市八幡町西乙原(にしおつばら)にいろいろな規模で同様の環流丘陵が分布している。 | |
| 見学地点の解説 | 河川の蛇行が大きくなり、蛇行部分が流路から切り離されて元の流路が直線的につながると、蛇行部分が曲がった流路の跡となる。平野部で起こるとそこが三日月湖として残されるが、山間部では流路跡に水が残ることはなく、そこは集落や田畑になり、それに囲まれた部分が丘陵として残される。これが環流丘陵であり、流路跡を還流旧河谷と呼ぶ。丘陵部は、美濃帯堆積岩類のチャートなどの硬い岩石が削られにくかったことで残されている場合が多い。還流旧河谷には河床礫が分布しているはずであるが、それらが露出して確認できる場合はほとんどない。保木脇地区では東海北陸自動車道が還流旧河谷部を通過していることで、その橋台下付近において河床礫の証拠となる円礫が地形的な高所にもかかわらず数多く見られる。 | |
| ジオの視点 | 山地部は平野部と異なり基本的に隆起地域であり、河川は大地を浸食して流下している。その場合、地質の硬軟や断層などの地質構造に規制されて削られていくことが多い。いったんできてしまった流路に即して、隆起運動で河川勾配が増大するのに応じて浸食作用が下方へも側方へも大きくなり、河川蛇行が成長していくことになる。浸食がすすんで蛇行部が切り離されて離水してしまうと、還流旧河谷や環流丘陵として残されるようになる。こうした地形は、長良川沿いのほか、静岡県の大井川流域、高知県の四万十川流域、和歌山県の十津川流域に多くみられる。 | |
| 写真 |  |
長良川に架かる立花橋からみた立花海上地区の環流丘陵 (撮影:小井土由光) |
| 写真 |  |
美濃市保木脇の東海北陸自動車道の橋台下でみられる円礫(河床礫) (撮影:小井土由光) |