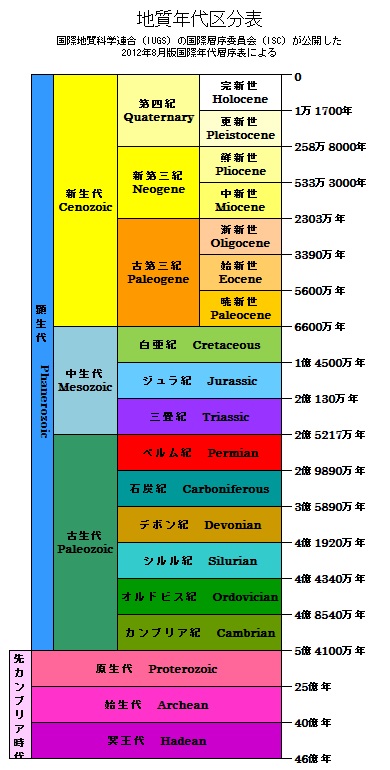| 項目 | 屏風岩 | びょうぶいわ |
| 関連項目 | 事項解説>景勝地・景観>渓谷・瀑布>中山七里 | |
| 地点 | 下呂市門原(かどはら) | |
| 見学地点の位置・概要 | 中山七里の中ほどにあたる下呂市保井戸は、渓谷としては比較的開けた扇状地をなす地形の場所にあり、ここから濃飛横断自動車道として馬瀬(まぜ)川方面へささゆりトンネル(国道256号)が貫かれている。国道41号を北上して、保井戸を過ぎてすぐ左手に国道より一段低い位置に旧道が残されており、そこに小さなトンネル(門原トンネル)がある。その付近から正面に見える巨大な岩壁が屏風岩である。 | |
| 見学地点の解説 | 巨大な岩壁はNOHI-4に属する高樽火山灰流シートの溶結凝灰岩からなり、縦方向に見られる割れ目は高温の火砕流が堆積後に冷えていく過程で体積が収縮してできる柱状節理である。この岩石は強く溶結作用を受けてかなり均質で厚い堆積物を形成していることもあり、しばしば大規模な柱状節理を形成することがある。屏風岩は遠望するだけとなるが、門原トンネルから少し屏風岩へ向かって歩くと、屏風岩と同じ柱状節理が国道脇でまじかに観察できる。 | |
| ジオの視点 | この大岩壁は、眺める上では景勝地となるが、険しい飛騨川沿いの街道にとっては交通の難所であった。実際にこの付近では、かつては道がきわめて狭く、飛騨川への転落事故が絶えなかった場所であった。旧道の門原トンネルはその改良工事として1916(大6)年に高樽火山灰流シートを掘削して完成した岐阜県下で最初の道路トンネルであり、これにより難所が解消されたとされている。 | |
| 写真 |  |
屏風岩の景観(左手前のガードレールの下に門原トンネルがある) (撮影:小井土由光) |
| 写真 |  |
門原トンネル (撮影:小井土由光) |