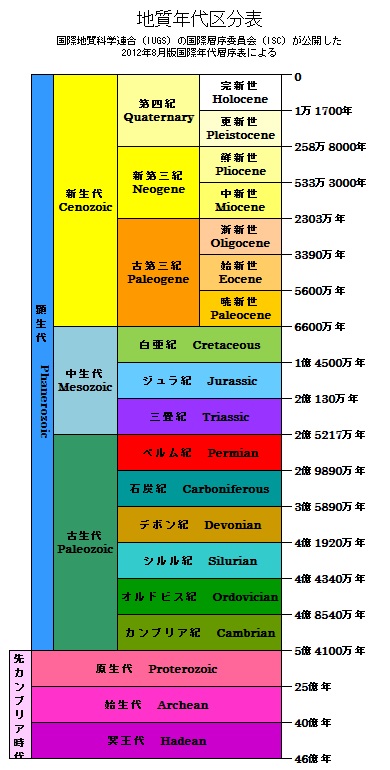| 項目 | 岩屋ダム | いわやだむ |
| 関連項目 | 事項解説>大型土木構造物>ダム>岩屋ダム | |
| 地点 | 下呂市金山町卯野原(うのはら)/乙原(おっぱら) | |
| 見学地点の位置・概要 | 濃飛横断自動車道のささゆりトンネルと和良金山トンネル(仮称)との間にある金山ICから県道86号金山明宝線を馬瀬川に沿って北上すると岩屋ダムのダムサイトに着く。 | |
| 見学地点の解説 | このダムは濃飛流紋岩が分布する地域に建設された多目的ダムであり、ダム堤体中心部の遮蔽層の上に巨大な岩塊を積み上げたロックフィル型ダムである。その巨大な岩塊はダム堤体から上流側右岸(左手)に見える大きなコンクリート壁のところで採掘されたもので、そこにはNOHI-4に属する堅硬な高樽火山灰流シートの溶結凝灰岩が広く分布している。その巨大ブロックの1つと思われる岩塊がダム堤体入口にある石碑「岩屋ダム」としてみられる。この岩石は約800mにも達する厚さで、しかもかなり均質な溶結凝灰岩層を作っており、多量の石英を含み、それらが2mmほどのよくそろった大きさで、ほとんど自形に近いこと、石質岩片をほとんど含まないことなどを特徴としている。見かけは貫入岩の石英斑岩に似ているが、レンズ状の本質岩片をともない、顕微鏡では明確な溶結組織が見られる岩石である。 | |
| ジオの視点 | ロックフィル型ダムに積み上げられる岩塊はその近傍に原石山を求めることから、それに適切な材料が得られる地質の場所に建設されることになり、ダムの堤体自体が周囲の地質を知る手がかりとなる。岩屋ダムでロックフィル型ダムが採用されているのは、おそらくは堤体を支える岩盤強度の問題よりは大容量の貯水を支えるためであろう。誕生した人造湖「東仙峡金山湖(とうせんきょうかなやまこ)」は424haの湛水面積で、飛騨川流域最大の人造湖である。 | |
| 写真 |  |
岩屋ダムの堤体 (撮影:小井土由光) |
| 写真 |  |
岩屋ダムの堤体入口にある石碑(高樽火山灰流シートの溶結凝灰岩) (撮影:小井土由光) |