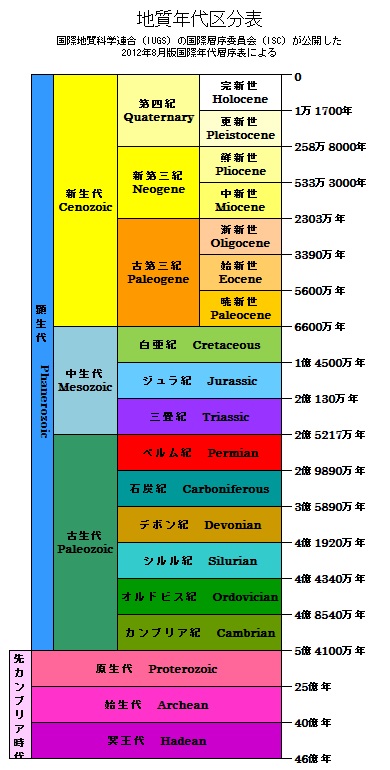| 項目 | 亜炭採掘口跡 | あたんさいくつこうあと |
| 関連項目 | 事項解説>鉱山跡・資源>エネルギー資源>御嵩亜炭鉱群 | |
| 地点 | 可児郡御嵩町比衣(ひえ) | |
| 見学地点の位置・概要 | 可児御嵩バイパスが通る以前の国道21号は、可児川を挟んでその北側をほぼ並走して御嵩町の中心街を抜けていた。その旧国道を東進し、東海環状自動車道の下を通過して最初のT字路を北進する。1kmほど進むと西側の山麓へ向けて耕作地の中を横切る細い道路があり、その突き当りに洞公民館がある。そこから2軒おいた南側に山への上り坂があり、100mほどで採掘坑道入口跡に至る。 | |
| 見学地点の解説 | 可児・御嵩地域の地下に広く分布している中村累層の褐炭層は、かつて亜炭として大規模に採掘されていたが、現在はまったく採掘されておらず、地下に多くの坑道が残されたままになっている。それらが地表の陥没を引き起こす“鉱害”を発生するようになっていることから、埋戻し作業が進められようとしている。御嵩町が一般市民向けに坑道内の見学会(平日のみ実施)を催しており、この坑口跡はその際の入口として利用している場所である(2016年現在)。通常は施錠されており、周囲に褐炭層(亜炭層)を観察するのに適当な場所もないことから、亜炭坑については「中山道みたけ館」で展示されている亜炭鉱山の坑内の様子を示す模型を参照するとよい。同館は名鉄広見線の御嵩駅からまっすぐ東へ200mほどのところにある。 | |
| ジオの視点 | 可児・御嵩地域の亜炭鉱は明治初期から採掘され、第2次世界大戦後の1947(昭22)年ごろの最盛期には全国産出量の1/4以上を占め、“炭鉱の町”として栄えた。しかし、燃料事情が好転するとともに需要が激減し、1968(昭43)年にはすべての炭鉱が閉山された。亜炭の採掘は、褐炭層の一部を柱状に残して坑道を支える「残柱方式」と呼ばれる方法でなされたため、その残柱部分が次第に劣化していくことで支えを失い、地表の陥没を引き起こす“鉱害”が発生するようになった。 | |
| 写真 |  |
御嵩町比衣にある亜炭鉱山の坑口跡 (撮影:小井土由光) |